

南では夏日なのに北海道では雪のニュースが! 記録を更新しつづけた暑い夏がやっと終わりホッとする間もなく、今度は昼と夜の寒暖差に右往左往する日々ですね。 今の時期は特に前線や突発的な台風による気圧のアップダウン、「初夏の陽気」とも言われるような日中の強い陽射し…かと思えば夕方の早い時間に日が落ちるので夜に向かって空気が一気に冷え、1日の温度差が10度を超える地域も多いようです。
野生動物はいち早く季節の移り変わりを察知して、今頃は冬ごもりに備えてせっせと食べ貯めていることでしょう。私たち人間は天気予報などで情報を知り、上着や冷暖房などで調整することができますが、そうして気をつけていても体調を崩しがちな季節です。 では、私たちと同じような環境に暮らしている犬や猫、小鳥や動物たちはどうなのでしょうか?
 セキセイインコや文鳥など小鳥は、温度の変化にとても弱い動物です。 特に寒さには敏感で、気温だけでなく人間たちに合わせてエアコンの効いた部屋などに入れるとすぐに体調を崩します。食欲が無くなり、体を膨らませてうずくまり、下痢や嘔吐、クシャミや鼻水が始まります。逆に暑さには強く、生活するには26~30度くらいの方が元気でいられます。秋から冬に向かい、苦手な寒い時間が増えていくので体調と環境のコントロールが難しいです。
セキセイインコや文鳥など小鳥は、温度の変化にとても弱い動物です。 特に寒さには敏感で、気温だけでなく人間たちに合わせてエアコンの効いた部屋などに入れるとすぐに体調を崩します。食欲が無くなり、体を膨らませてうずくまり、下痢や嘔吐、クシャミや鼻水が始まります。逆に暑さには強く、生活するには26~30度くらいの方が元気でいられます。秋から冬に向かい、苦手な寒い時間が増えていくので体調と環境のコントロールが難しいです。
猫は1日の日照時間の変化を感じて、春と秋に発情期を迎えます。 雄同士は激しく叫びながらケンカを繰り返し、雌は食欲が減退するとともに落ち着きがなくなります。 室内100%の猫はこの発情の時期に脱走して迷子になったり、ケンカによるケガで発熱や化膿などのトラブルが増えます。また、望まない妊娠や、ケンカの傷から猫のエイズや白血病など伝染病にかかるケースも多いです。 これらは、不妊手術や去勢手術で回避することが可能ですが、それでも季節に影響を受けて何となく様子がいつもと違う子もいます。
梅雨時には消化器系の不調や皮膚病などに注意が必要でしたが、カラッとした秋口の気温差にはまた別の心配がでてきます。空気が乾燥して陽射しが強い日中には脱水しないように新鮮なお水をたっぷり置いておきたいのですが、水分を摂り過ぎると、今度は朝晩冷え込む時間に不要な水分が体の中に溜まったままになり代謝が滞ってしまいがちです。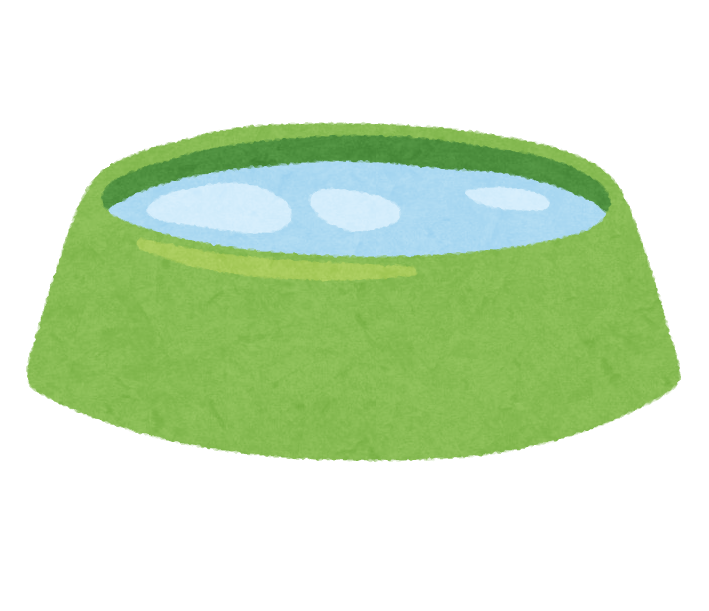 暑い日中に水分を制限するのは危険ですが、摂り過ぎるのも考えものです。
暑い日中に水分を制限するのは危険ですが、摂り過ぎるのも考えものです。
犬も猫も寒くなってくると、じっとしている時間が増えて運動しなくなります。 動かないので食欲が落ち、食べても消化しづらく吐いたり下痢したり、といった症状につながります。 1年中同じメニューではなく、こんな時期には消化の良い食餌をいつもより少なめにして与えるなどの工夫が必要です。 食べる量が減るというのは、皮膚や被毛など体全体に栄養が十分に行き渡らないということでもあるので、犬や猫の年齢と体質に応じた消化の良い食事を探したいですね。
毛艶が悪くなったり、皮膚がカサカサして皮膚炎にもなりやすい
![]()
良質のサプリメントなどを追加
免疫力
犬も猫も全体的に尿量が少なく
膀胱炎
尿路結石
トイレの回数や尿の変化などに注意
![]()
運動量とトイレのチャンスを増やす
季節の変わり目の「寒暖差」は、犬や猫の体にとっては大きなストレスでもあります。 犬の気管支炎や、猫風邪とも呼ばれる猫のインフルエンザ、その子が元々持っている病気なども発症しやすくなるので気をつけてください。
 温度変化の「差」をなるべく減らしてストレスを軽減しながら、冬に向かってゆるやかに体が準備していけるような環境を作りたいですね。 日中はカーテンを利用したり、夕方からはホットカーペットや加湿器などをうまく使って、過剰にならない程度に調節してあげてください。時々体を触ってみて、冷えすぎていないか、日なたに長時間居過ぎて脱水していないかもチェックした方が良いでしょう。 少し過保護に感じるかもしれませんが、特に仔犬や仔猫・老猫や老犬は季節の変わり目だけでなくちょっとしたストレスであっても大きく体調を崩します。ストレスの少ない環境とともに、普段から免疫力をキープして、いざという時にはストレスに立ち向かえる体作りも必要です。
温度変化の「差」をなるべく減らしてストレスを軽減しながら、冬に向かってゆるやかに体が準備していけるような環境を作りたいですね。 日中はカーテンを利用したり、夕方からはホットカーペットや加湿器などをうまく使って、過剰にならない程度に調節してあげてください。時々体を触ってみて、冷えすぎていないか、日なたに長時間居過ぎて脱水していないかもチェックした方が良いでしょう。 少し過保護に感じるかもしれませんが、特に仔犬や仔猫・老猫や老犬は季節の変わり目だけでなくちょっとしたストレスであっても大きく体調を崩します。ストレスの少ない環境とともに、普段から免疫力をキープして、いざという時にはストレスに立ち向かえる体作りも必要です。